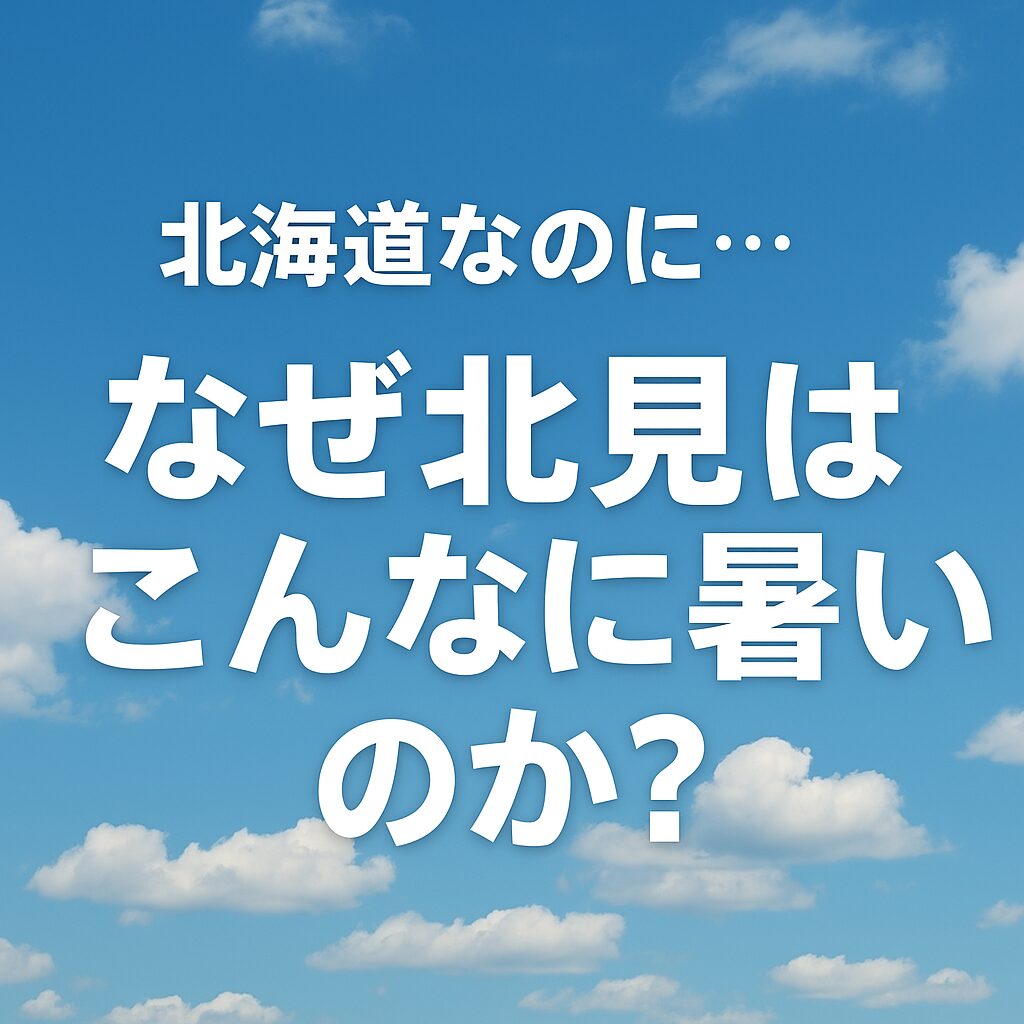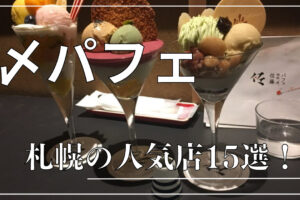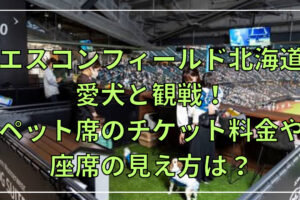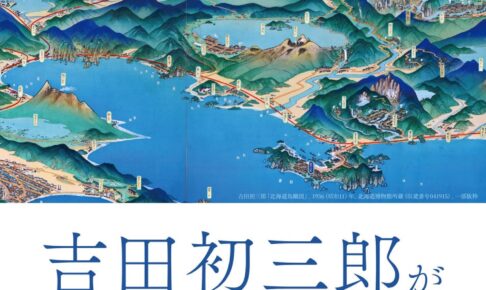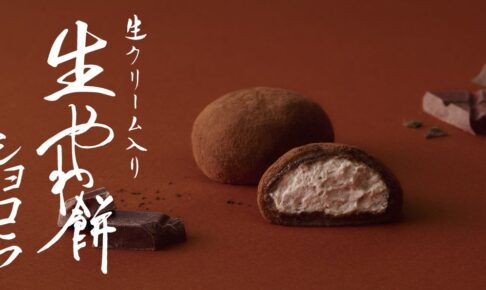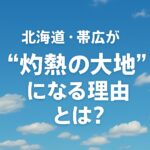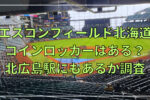北海道といえば「涼しい避暑地」のイメージが強いですよね。
ところが、毎年のように猛暑日(35℃以上)を記録する都市が、道東にあるのをご存じですか?
それが、北見市です。
夏になると、「北海道なのにこんなに暑いの!?」と驚く声がSNSを賑わせることも。
一体なぜ、冷涼なイメージのある北海道の中で、北見だけがこんなにも暑くなるのでしょうか?
この記事では、気象データや地形、風の流れなどの科学的根拠に基づいて、北見の暑さの秘密を徹底的に解説します。
きっと「なるほど!」と納得できる理由が見えてくるはずです。
1. 内陸性気候による寒暖差の大きさ
北見市は北海道の中でも内陸部に位置しており、海の影響を受けにくい地域だよ。これが大きな寒暖差を生む原因になってる。
海沿いの地域は、海が気温を安定させる「緩衝材」となるため、夏も気温が上がりにくい。
でも内陸は日射の影響をダイレクトに受け、昼間の気温がぐんと上がる。
特に放射冷却が効く朝晩は気温が下がるため、日中との寒暖差が大きくなる。
科学的根拠
内陸性気候では地表面の加熱・冷却が極端で、昼夜・季節間の気温差が大きい(気象庁資料による)。
北見の年平均降水量は少なく、湿度が低いため、熱がこもりやすい。
2. フェーン現象の影響
北見周辺では、特定の気圧配置のもとでフェーン現象が発生しやすいのも特徴。
フェーン現象とは:山を越えて風が吹くとき、風の下り坂側で乾燥しつつ気温が上がる現象。
北見の西側には石北峠(せきほくとうげ)などの山地があるため、風が山を越えるとフェーンとなり、北見では異常な暑さになることがある。
具体例
2021年6月9日:北見で35.2℃を記録。このときは、日本海側からの乾いた南西風が山を越えてフェーンとなり、北見に熱気をもたらした(気象庁の実況解析より)。
3. 盆地地形が熱をため込む
北見盆地は周囲を山に囲まれた地形で、空気の流れが滞留しやすい。
昼間に太陽で熱せられた空気が、逃げにくい。
また夜間も熱が地面や空気に残り、熱の蓄積が翌日以降に影響を与える。
このため、連日30℃を超える「真夏日」が続きやすいという傾向があるんだ。
4. 地球温暖化の影響も無視できない
ここ10〜20年で、北海道全体の平均気温が上昇してるのも大きい。特に夏の高温化が顕著で、「北国だから涼しい」というイメージは過去のものになりつつある。
気象庁の長期統計(1980〜2020)によると
北海道の夏季平均気温は約1.0〜1.5℃上昇。
極端な高温日(猛暑日)の頻度も年々増加傾向。
5. 都市化によるヒートアイランド効果(局地的要因)
北見市中心部は人口約12万人と中規模都市で、アスファルトや建物が多くなってる。これが熱の蓄積と再放出を促し、特に夜間の気温を下げにくくしてる。
まとめ:複合要因で北見は「暑い」
・内陸性気候 …海の影響を受けず、日射の影響を強く受ける
・フェーン現象… 山を越えた風が熱風となって流れ込む
・盆地地形… 熱がこもりやすく、空気が滞留しやすい
・地球温暖化… 年々、夏の気温が高くなる傾向
・ヒートアイランド現象 …都市部での人工物による熱の蓄積